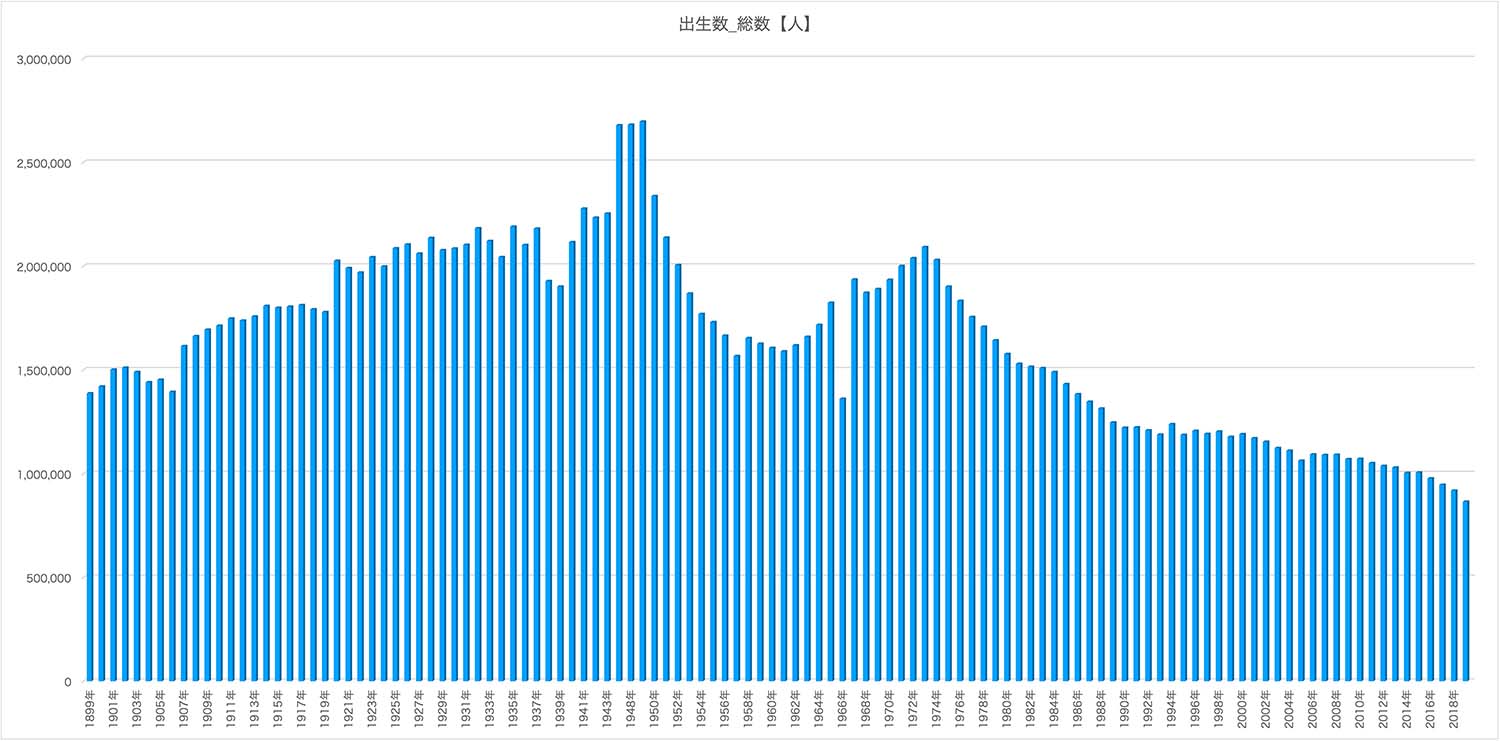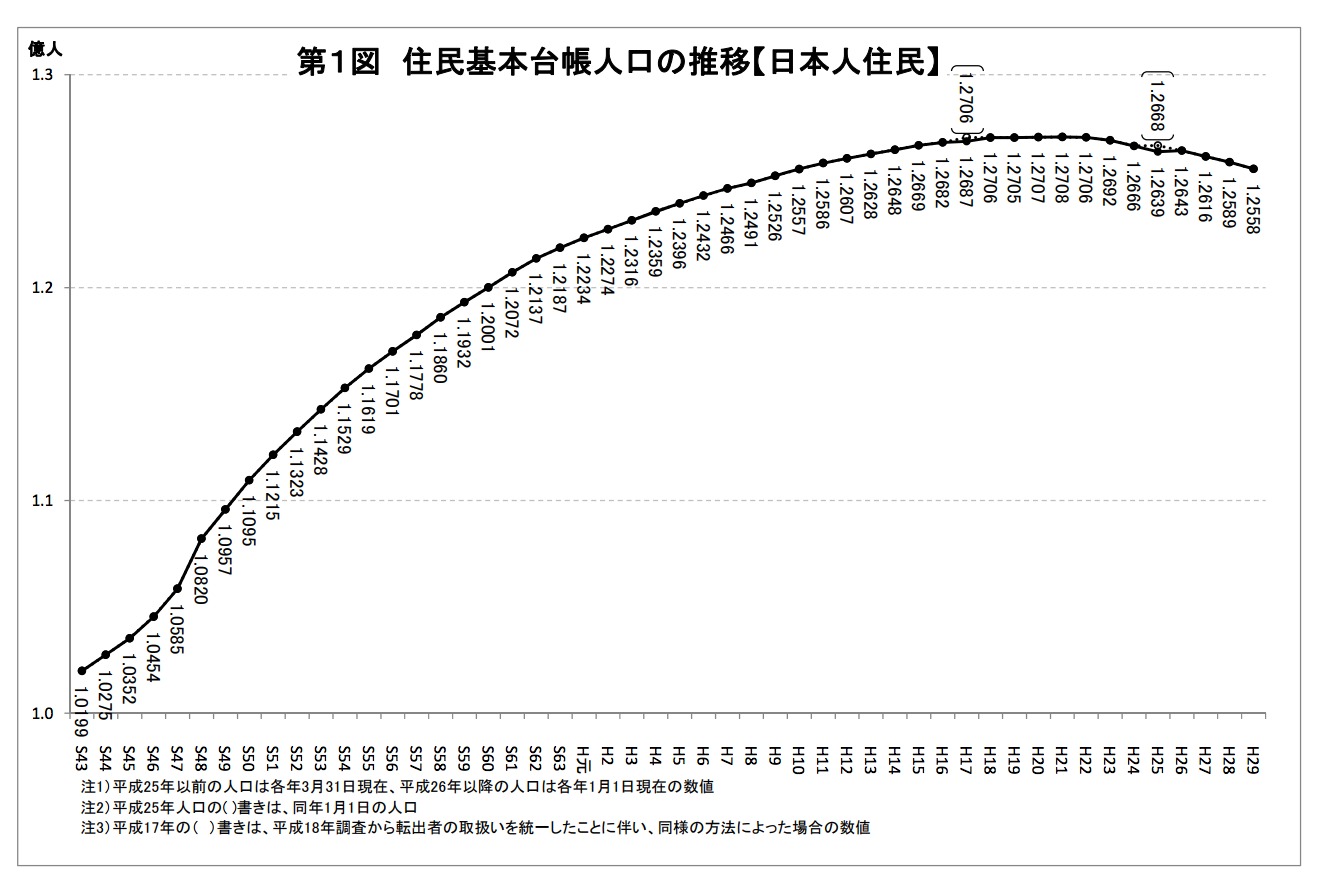2011年の人口動態統計が発表されました。
自然減が20万人。
戦後最大幅。
人口減少は2007年以降、連続5年で減りました。
2011年の出生数は105万7千人。
これも戦後統計を取り出した1947年以降で最低。
旧少子化社会白書を調べてみます。
↓ 1920年からの人口構造グラフ。
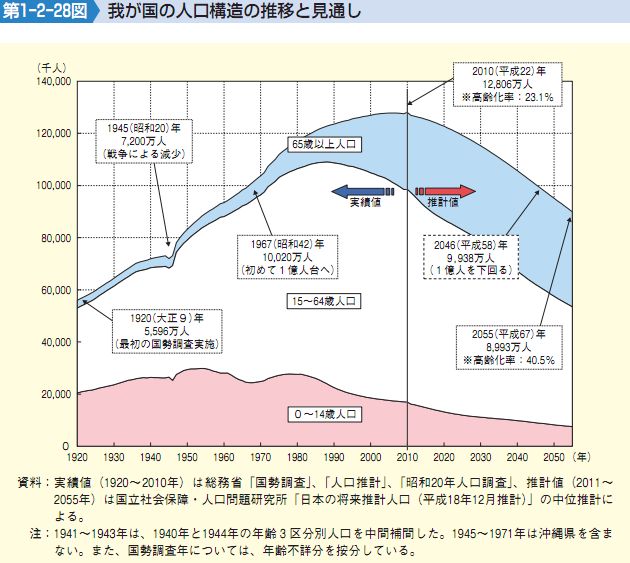
戦後1945年には人口が7200万人。
5年前のピーク時には1億2620万人。
約60年で1.75倍になったのです。
日本の高度経済成長や景気はこの人口増加とも
連動していたことがわかります。
他にも人口動態は企業の経営にも大きく影響を
与えてきます。

上記は、労働力の推移と見通しのグラフ。
2000年の6766万人
2006年の6657万人
が実績値として出ています。
2000年 → 2006年で
109万人の減少。
100万人以上の労働人口が減少しているのです。
今後、減り続けたときに、2030年には、
2000年と比較して1割から2割の減少が
見込まれます。
実に、486万人の減少から1182万人の減少が
予測されているのです。
減少幅が広いのは、労働市場への参加が
進む場合と進まない場合が予測されています。
「働く意欲」が社会的に高くなるのか、低くなるのか、
大きな差がここでも出てきそうです。
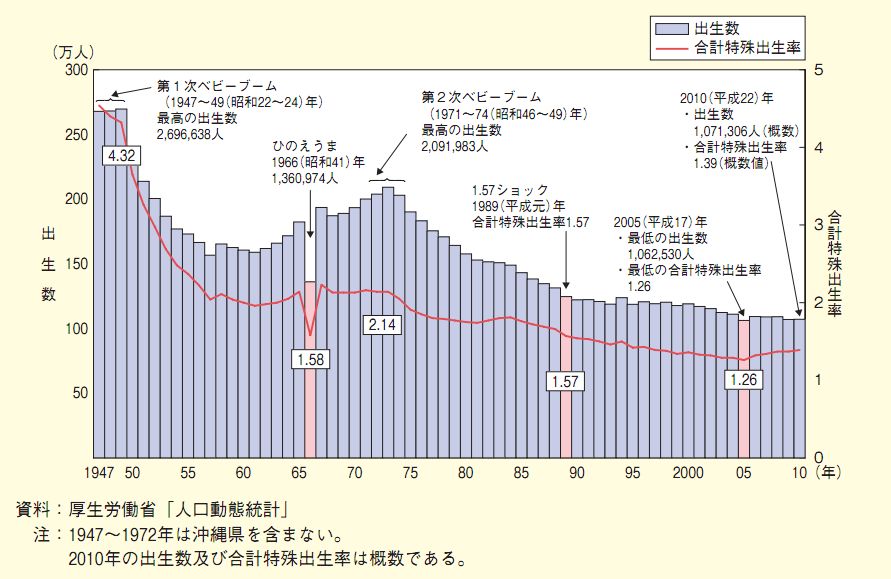
会社の経営においては、
人材採用がより難しくなること
組織の年齢構成がアンバランスになること
が懸念されます。
採用方法も新卒採用、中途採用という枠ではなく
【通年採用】
が広がるでしょう。
そのため人材系のビジネスは、大きく変化します。
これだけ人材採用がミスマッチを
起こしている現状を見ると、遅かれ大きな構造変化が
起きてきます。
どの会社からイノベーションが起こるのか
見ていきたいところです。