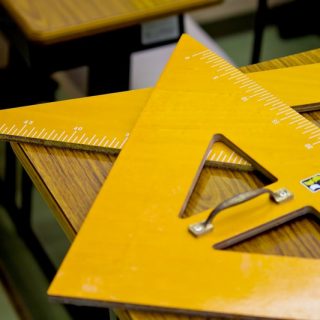【fjconsultants365日Blog:3,777投稿目】
〜1日3分、3ヶ月で1冊分の知識転移〜fjコンサルタンツ藤原毅芳
リアルタイム フィードバックとは
評価は年2回だけ、という会社が普通でした。
しかもその時に面談をするのですが中身は評価点を伝えるだけ。
そんな感じでした。
これが今では頻度が見直されています。
フィードバックの頻度が上がると「リアルタイム フィードバック」と
呼ばれるようになっています。
そこで新たな課題が出ています。
フィードバック手法について問題が起こっているのです。
それはどのような内容か。
どんな課題か。
フィードバックの方法が少な過ぎることが問題を引き起こしています。
フィードバックの回数が増えているのに効果が上がらないという現象。
ここです。
回数を単純に増やせばいい、というものでもない。
しかし、少ないよりは多い方がいい。
フィードバックの回数を増やし更に効果を上げることを今回は
考えてみたいです。
結果、リーダーの時短につながることを目指します。

フィードバックのコツ
フィードバックにはコツがあります。
「①伝える」「②気付かせる」の2つ。
シンプルにこの2つに集約して考えるとわかりやすい。
そもそもフィードバックとは
1 . 【情報通知 】たとえ耳の痛いことであっても 、部下のパフォ ーマンス等に対して情報や結果をちゃんと通知すること (現状を把握し 、向き合うことの支援 )
「フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術」
2 . 【立て直し 】部下が自己のパフォ ーマンス等を認識し 、自らの業務や行動を振り返り 、今後の行動計画をたてる支援を行うこと (振り返りと 、アクションプランづくりの支援 )
(PHPビジネス新書) 中原 淳 著
です。
そのためには、
- ①成長ポイントを伝えること
- ②改善点を気付かせること
だけなのです。
それ以外はいらない。
必要がないのです。

時短でフィードバック
働く時間は短くなる一方で求められることは変わらない。
いや、今以上に求められているケースもあります。
世の中が高度化しているのです。
では、どうすればいいの?
教育する時間はない。
ほったらかし教育でいくしかない?
育つか育たないかは本人の問題だし。
まあ、いいか。
そんな感じになります。
そこで提案。
フィードバックに時間をかけず回数を重ねる戦略で育てる。
これがいまのベストです。
常に一緒にいると思うな
常に一緒にいる。
いつでも話しができる。
顔を見ることができる。
だから時間をかけ過ぎるのです。フィードバックに。
そこ、気が付いてますか。
1週間に15分しか時間がないとしたら。
1ヶ月に30分しか時間が取れないとしたら何を伝え、何に気付いて
もらいたいですか?
そう考えることです。
この考え方が起点となるならばフィードバックに時間をかける
ようなことはしません。
時間は有限であり最大の資産。
最大効率で運用すべきです。

①伝えるとは
フィードバックのポイント「伝える」「気付かせる」について
具体的に見ていきます。
伝えるとは、
- 成長ポイント
- 課題点
- 問題点
のポイントを相手にダイレクトに言うことです。
時には指摘する場合もあります。
周りから見て気になっているが本人は知らない領域を示すこともある
のでダイレクトに言うことになります。
伝えるにはコツがあります。
冷静に数値を用いて伝えること。
客観的事実として伝えます。
「これ、8件だったよね」
とだけ伝える。
「だからダメなんだ」とは付け加えない。
「他のメンバーは12件やってる」
と数値で伝えるだけにするのです。
これ以外、他のことは何も言わないこと。
伝える側(リーダー)の感情や感想を言う必要はゼロ。
それでいいのです。
②気付かせるとは
気付かせるとは
- 改善点
- 修正点
について本人自身が答えを導くことです。
①で伝えられたことについて、ここで解決するプロセスを見つけること。
その作業なのです。
逆にここでは①と違って周りは答えを言ってはいけません。
投げかけだけをして時間をおくことです。
その間に本人は自分だけで答えを導き出していくのです。
人は他人から言われた通りに動いただけで成長はしません。
自ら発見する、探し出すというプロセスが成長のエンジンなのです。
まとめ
フィードバックには
- ティーチング
- コーチング
の2つの要素があることに気が付きます。
「①伝える」ときは「ティーチング」で
「②気が付かせる」ときは「コーチング」で
行うということ。
この使い分けを意識すればするほど、教育の効率が上昇します。
時短につながります。
そう、教育は教える時間と成長結果は比例しません。
教える時間が長すぎるほど反比例することもあると考えています。
ちょうど働き方が時短へと移行するときですから教えることも
効率を求めていくのもひとつの方法だと思います。