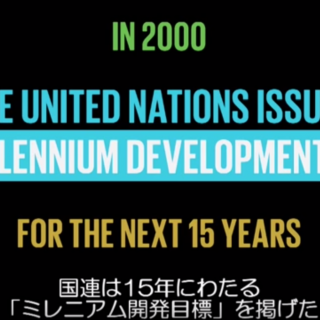【fjconsultants365日Blog:4,029投稿目】
~経営には優先順位がある~経営コンサルタント藤原毅芳執筆
人は予測しながら生きている
ストレスを感じるとき。
それはどんなときか。
ひとつには、自分が予測していた状況とは違う場面展開に
なったとき。
予想外、想定外のとき、大きなストレスを感じる。
人間関係でも想定と違う反応をされるとストレス値は
マックス(最大 Max)に近づいていく。
そう考えると、ヒトは予想範囲内で生活したい、仕事したい
動物だと感じます。
想定外のことが発生しないように防御する。
守りに入る。
無意識だと予測できる範囲に落ち着いていくのです。

リーダーになると予測しなくなるのか
会社組織では、会社の成長速度に遅れを取るリーダーが
います。
会社の成長に合わせて成長するはずなのに、リーダーの
成長がない。
見えない。
人は予測しながら生きているはず。
リーダーとしても、ここまでやれば、今年はココまで到達する
だろうと予測して仕事をするはず。
それがない。
予測が「現状維持」「このままでいけるだろう」になっており
去年と同じことを続けています。
現状維持という予測だから伸長率が限定されてしまう。
限りなくゼロに近くなるのでしょう。
会社の成長スピードが速い企業ではリーダーの入れ替わりが
数%の率で発生します。
本人から「リーダーをおろしてほしい」と言い出す。
その原因は、単に「成長スピード」の差異が大きくなっただけ。
ある意味、健全な形かもしれません。
成長スピードがない企業ではリーダーが入れ替わることが全くない。
それはそれで、「成長していないかも」と考えることです。

どう予測すればいいのか
予測する技術とは何か?
何のスキルが必要なのか?
リーダーの予測が外れる事例から考えてみます。
リーダーの予測が外れるとき、発生していることは
過去のできごとから、将来が同じ延長線上で発生すると
考えていること。
「そんなこと、されたことない」
「今まで、そんな事は一度もなかった」
と口走るとき、過去から引いた補助線を忠実にたどりながら
仕事していることに気がつきます。
あくまでも補助線は補助線。
本線ではありません。
その上を行くときもありますが、補助線から外れることも
あるのです。
予測する技術とは、
・補助線を増やすこと
です。
補助線を増やせるチカラをつけることなのです。
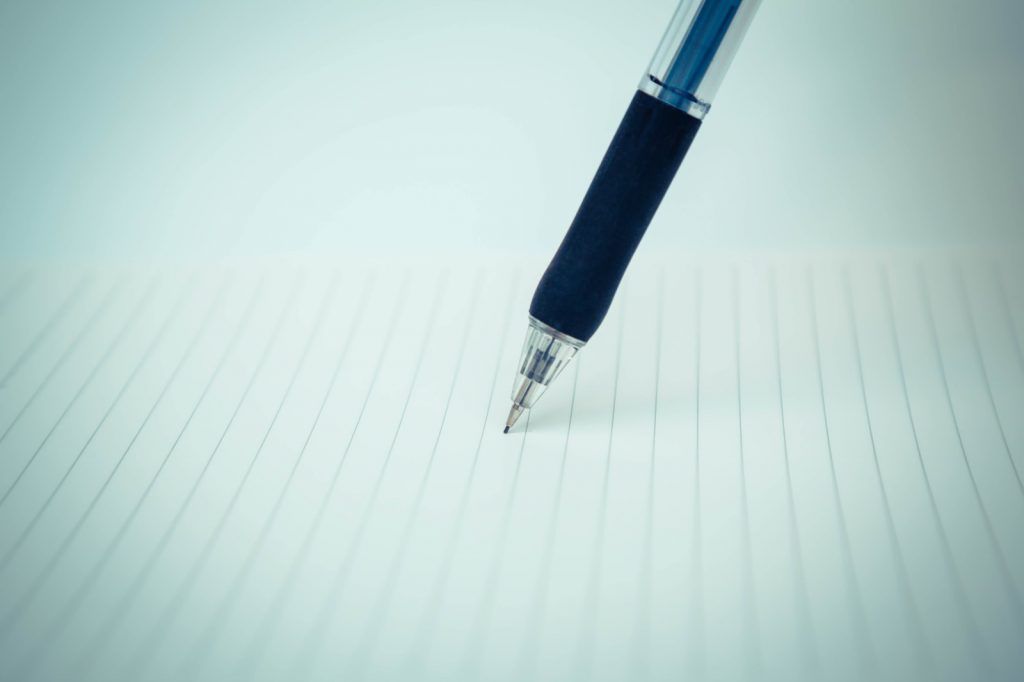
まとめ
「もし、このままうまくいったらいいなあ」と
考えるときは、いつまでも頭の中で考えを巡らせます。
「ひょっとすると、こんないいことも発生するかも」
と、プラスなイメージはとどまることを知りません。
しかし、マイナスな局面はさほどヒトは考えない。
「昨日も今日と同じだった」
同じ毎日が続くほど、マイナスなことは発生しないように感じる。
だから、マイナスな場面は考える必要がない。
10年に1度しか発生しないことを考えても疲れるだけ。
そう思えるでしょう。
ムダに感じることでしょう。
ただ言えることは、予測領域の面積が大きい人ほど、
対応力が速く、失敗確率も低い。
それだけのことなのです。
しかし、欠かせない部分でもあるのです。