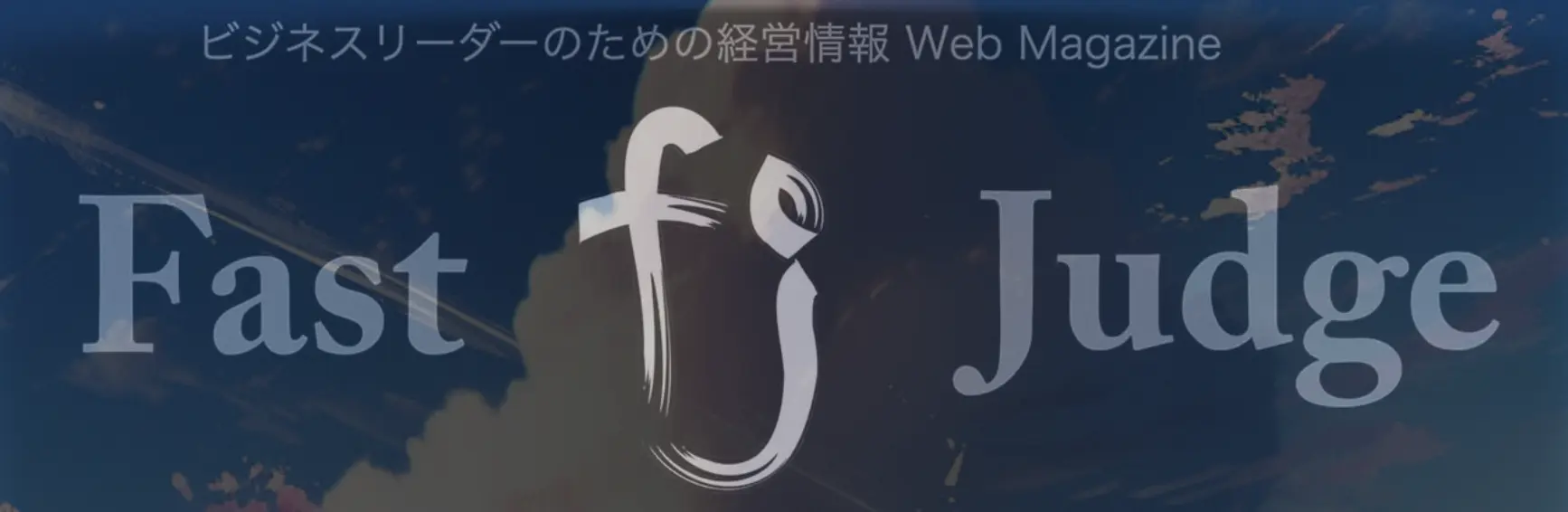- 更新日:
- 公開日:
出生数については定点観測しているのであまり驚くことではありませんが、2022年は出生数が80万人割れになるかもしれないようです。

- 更新日:
- 公開日:
2022年11月に発売された「白湯」。ペットボトルの天然水。コンビニエンスストアのホットドリンクの棚に並んでいます。

- 更新日:
- 公開日:
気遣いレベルアップさせるには何を教えたらいいのでしょうか。「気がきく人になれ」と言っても、その通りに成長することは少ない。

- 更新日:
- 公開日:
人工知能AIの進化が一気に進んだ感があります。実用化され始めたAIが増えています。

- 更新日:
- 公開日:
スタートアップ界隈では話題になっています。2022年11月28日に開催された新しい資本主義実現会議第13回の内容についてです。スタートアップ育成5か年計画が具体的に開示されたのです。

- 更新日:
- 公開日:
日銀が2020年から実施している地方銀行支援先が91になりました。増加傾向にあります。

- 更新日:
- 公開日:
忘年会の予約状況が公開されています。以前の7割まで回復しているようです。この忘年会予約の状況をどう読み取るのか

- 更新日:
- 公開日:
ジャイアントキリングという単語が出てきました。ジャイアントキリングとは、大番狂せという意味。勝てないと思われた試合で勝ってしまうことを指しています。

日銀が想定しているデジタル円はCBDC(Central Bank Digital Currency)と呼ばれています。まだ現在は発行する計画はありません。
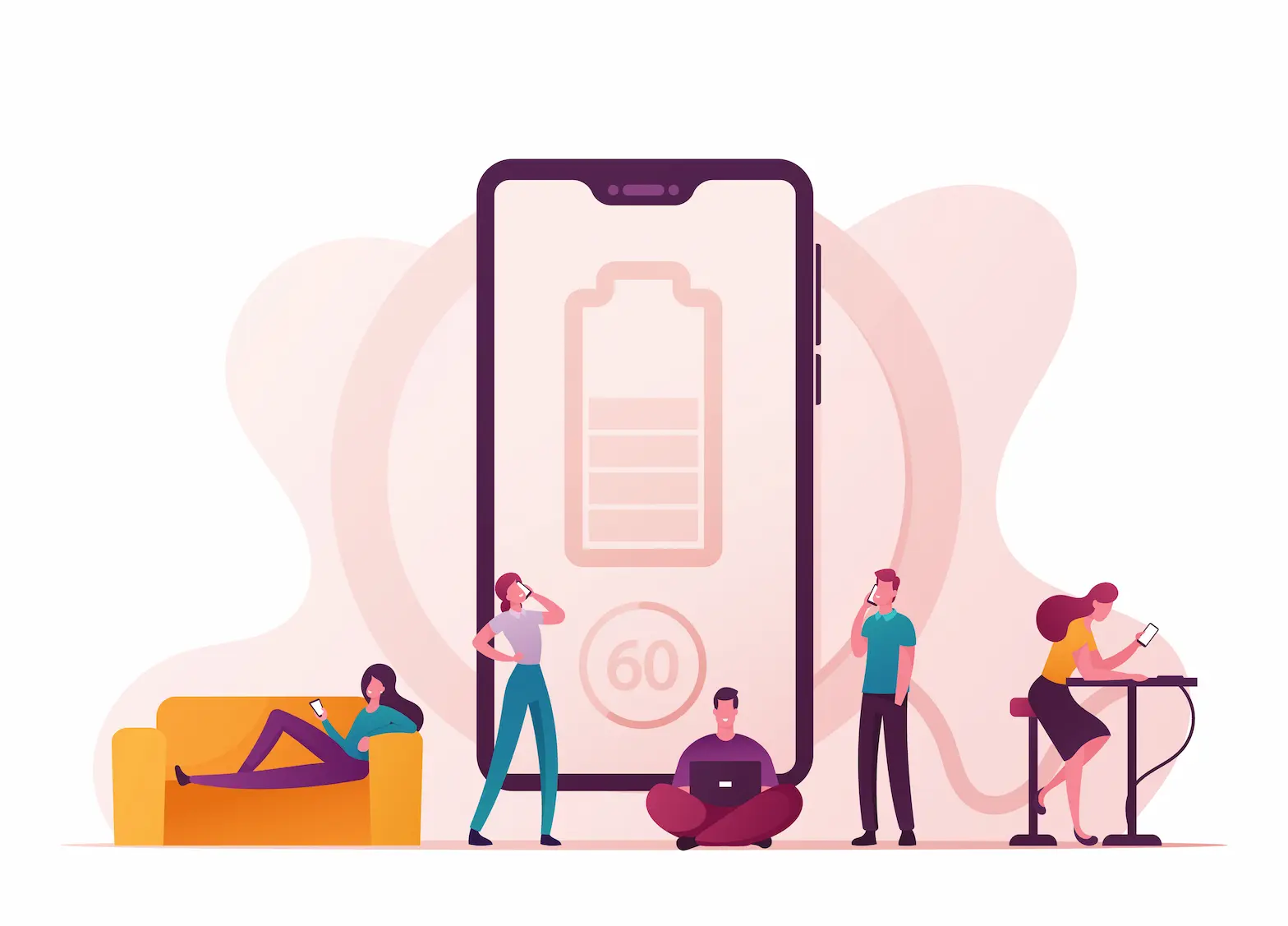
ひとりで仕事を抱えてパンクしている人が出てきました。ストレスを溜め込んでいる人もいるようです

- 更新日:
- 公開日:
現在利用されている太陽電池は「シリコン系太陽電池」です。丈夫であり変換効率も低くはありません。おおよそ25%程度の変換効率を保っています。

- 更新日:
- 公開日:
販売手法は便利さに傾いてきましたが製品飽和で便利さは《飽き》も生じさせることになってしまいました。店